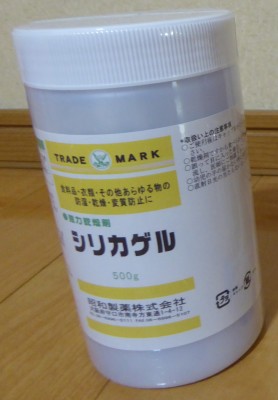ポンプ
楽天市場で買いました。2,397円でした。
ストーン付きです。
いろいろあって迷いましたが、電池での長時間駆動が可能ということと、流量が多め(1.2L/min)という点で選択しました。
類似品のダイヤフラム式よりロータリ式の方が音が静かかな?ということも期待した点です。
音の方は聞こえますが、観測中はまったく気にならないレベルでした。
|

|
つなぎ(ニップル)
ネジで固定できる隔壁用を買おうかと思いましたが、たいした圧力ではないだろうし、これで済ませました。
|

|
L字ニップル
フードへの取り付けはあまり出っ張りが無い方がいいだろうと、L字型も購入。
|

|
(2液式)エポキシ接着剤
ニップルを固定し、隙間を充填するのに使います。
|
写真なし
|
エアホース(黒)
最初は透明を買いましたが、フードへ取り付けした際に透明だとホースを伝って光が漏れてくるので、黒に変えました。
|

|
アルミテープ
フードへ使ったL字ニップルがプラスチック製であったため、そこからの光の漏れこみが問題になり、その遮光用です。
|
写真なし
|
蓋つき瓶
なるべく大きい方がよかったのですが、たまたま手元にあった瓶を使いました。
透明な瓶の方が、シリカゲルの様子がわかりやすくていいと思います。
|

|
シリカゲル
値段(629円/500g)につられて購入しましたが、全部が青色のシリカゲルの方がいいと思います。
|
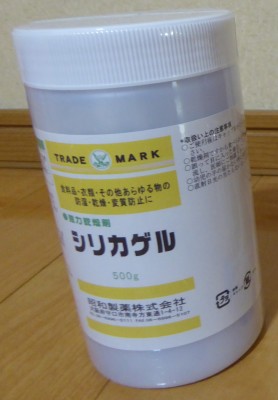
|
三つ又分岐ニップル
今回、乾燥空気をフードの2か所へ導くようにしたかったので、分岐用のニップルも用意しました。
|
写真なし
|

|
シリカゲルを入れる瓶の蓋にニップルを取り付けるための穴をあけます。
|

|
細い穴であけてから、太いドリルに変えて、追い込んでいきました。
このように2つあけます。
|

|
開けた穴にニップルが取り付け可能なことを確認したのちに、エポキシ接着剤で固定します。
今回は、穴を追い込んであけたことで、かなり固めのほぼぴったりサイズ、エポキシ接着剤は、このように先に蓋の穴周辺に塗っておいて、そこにニップルを差し込むことで隙間がきれいに充填できます。
一応、瓶内に微小ながらも内圧がかかるだろうとニップルは蓋の内側から取り付けました。
|

|
乾燥したら、このように接続して、完成です。
エアポンプから接続するホースの先にストンをとりつけます。もう一方のニップルの先に望遠鏡を取り付ける形です。
この後、瓶の中にシリカゲルを入れます。
想像できると思いますが、シリカゲルを入れたあと瓶のふたを閉めるのが結構大変です。
もしあれば、蓋は機密が保てた上で、ねじ込み式ではないものがいいと思います。
|

|
次に、フードへエアホース接続用のニップルを取り付けます。
|

|
取り付けはなるべく望遠鏡側になるように、あけました。
|

|
このL字ニップルを取り付けます。
後で気が付きましたが、金属製のニップルの方がいいです。
というのも、このプラスチックは光を少し透過しますので、せっかくのフードの側面から光が漏れこむ危険性があります。
|

|
ニップル取り付け後
黒で塗装してみましたが、簡単にはがれるので、のちほど改良。
ニップルはフードの180度位置、2箇所に取り付けました。
|

|
ホースを取り付けるとこんな感じ
|

|
これが改良後です。
光の漏れこみを防ぐためにアルミテープを巻いてみました。これでフードの中から覗いても光の漏れこみはありませんでした。
|

|
これが完成状態です。
シリカゲル瓶からのホースを途中で三つ又を使って分岐させて、フードの2か所へ供給できるようにしました。
|